大和へ届け、沖縄の心
ヤマトへとどけ しまぬくくる
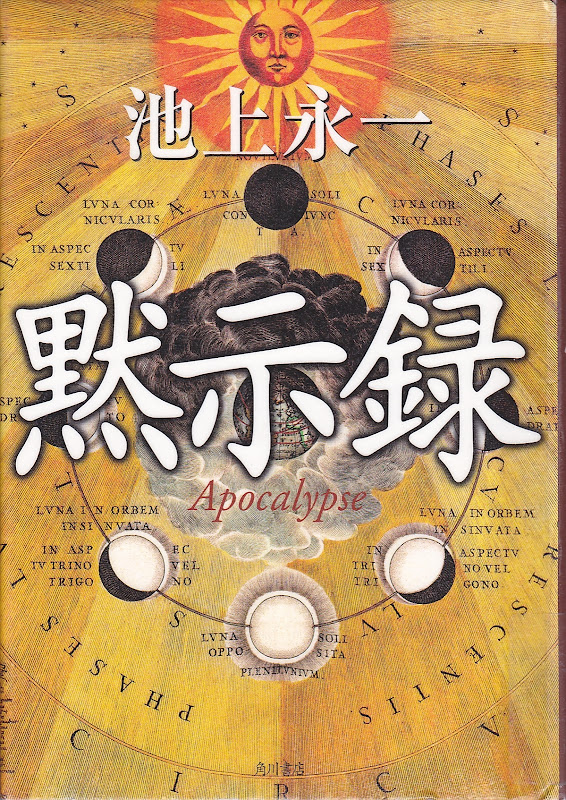 |
琉球に生まれた天才舞踊家の、壮絶なる«天国»と«地獄» 18世紀の前半、那覇の街に蘇了泉という貧しい少年がいた。王府の踊奉行に才能を見出された了泉は生きるため、絢爛たる舞踊の世界に飛び込む。 その先に待っていた運命とは-。協力者と敵対者、そのすべての運命を呑み込みながら、ひとりの天才舞踊家が琉球に嵐を巻き起こす! テンペストを凌ぐ池上サーガの至高の到達点!!(装丁帯より) (あらすじ:まな兵衛) 琉球は士族と百姓の階級社会、その下に非人の乞食がいる。彼らは念仏者(ニンブチャー)として貧民の葬儀と埋葬を生業とする。 そのニンブチャー部落から不業の業病に冒された母とともに追い出され、那覇の市で曲芸一座の呼び込みで一日の糧をかろうじて稼ぐ乞食少年がいた。 その了泉の素早く生き生きとした動きを王府の踊奉行が目をつけ弟子として舞踊を仕込む。 やがて了泉は楽童子として江戸上りで天才ぶりを発揮し士族に出世する。 王府で組踊の創始者に見出され活躍するが冊封使の歓迎式典で失敗した了泉は義父を殺し元のニンブチャーに貶される。 初心に戻った了泉は最下層の社会で黙々と舞踊に励み、久高島のノロに学びついには斎場御嶽で太陽しろの王の月しろの至高に至る。 |
| なわしろのみやに 月しろはてって つきしろす なさいきょもいまふりよわめ けふのよかるひに |
苗代の庭に 月しろは両手を重ね 月の光が 祈るように降り注いでいる 今日の吉かる日に |
| 旅ぬ出立ち 観音堂 千手観音 伏し拝で 黄金杓取て 立ち別る 袖に降る露 押し払い 大道松原 歩み行く 行かば八幡 崇元寺 |
|
美栄地高橋 うち渡て 袖を連ねて 諸人の 行くも帰るも 中の橋 沖ぬ側まで 親子兄弟 連れて別ゆる 旅衣 袖と袖とに 露涙 |
| 上り口説(ヌブイクドウチ):二才(ニセー)踊り | ||
| 打ち鳴らし 打ち鳴らし サーセンスルセンスルセー 四つ竹は 鳴らち サーセンスルセンスルセー |
今日や御座御座出でて 遊ぶ サー 遊ぶ嬉りさ 今日や御座御座出でて 遊ぶ サー 遊ぶ嬉りさ |
|
| 踊りくわでさ節(女踊り) | ||
| シュンドー 諸屯長浜に ヨー アシュンドー 打ちゃる引く波ぬ ヨー アシュンドー 諸屯女童ぬ ヨー アシュンドー 目笑れ歯くち ワタチャンドー アシェウキトクサ |
シュンドー 諸屯女童ぬ ヨー アシュンドー 雪ぬるぬ歯ぐち ヨー アシュンドー いつか夜ぬ暮りて ヨー アシュンドー 御口吸わな ワタチャンドー アシェウキトクサ |
|
| ↑諸屯節(打組踊:美女) | ↑スリカン節(打組踊:醜女) | |
| 油買うて給れ ぢふぁん買うて給れ ンマサミ 捨て夫の見る前 身なでしゃべら スリカン |
阿旦垣でいんす 御衣掛け引ちゅり ンマサミ だいんす元びれや 手取て引ちゅさ スリカン |
|
| 打組踊:前組踊、玉城朝薫創始 | ||
|
御慈悲ある故ど イヤイヤ 吾無蔵ガヨー 御万人のまぎり イヤイヤ 吾無蔵ガヨー 上下も ヒヤーマーター 揃て アスシュラヨー |
仰ぎ拝む フイ 嬉サミ フイ シュラ ジャンナーヨー ハイヤ 嬉サミ シュラヨー フイ |
|
| 女特牛節(イナグクテイブシ:女踊) | ||
| 思事のあても ヨー よそに語られぬ 面影と連れて 忍で拝マヤーゥーンナー 枕並べたる ヨー 夢のつれなさよ 月や人下がて 冬の夜半 アリ里主ヨー |
別れて面影の 立たば伽めしやうれ 馴れし匂ひ袖に 移ちあもの ヨーンナー サーサー ションガネー スーリー ションガネー |
|
| 諸屯節(入羽の踊) | ||
| さても旅寝の仮枕 夢の覚めたる心地して 昨日今日とは思へども 最早九十月なりぬれば やがて御暇下されて 使者の面々 皆揃て弁財天堂伏し拝て いざや御仮屋立ち出でて 滞在の人々引き連れて 行屋の浜にて立ち別る 名残り惜しげの船子ども 喜び勇みて 帆揚ぎぬ 祝の杯回る間に 山川港に走い入りて 船の改み 済んでまた 錨引乗せ真帆引けば 風やまともに子丑の方佐多岬も後に見手 七島渡中も安々と |
浪路はるかに眺むれば 後や先にも友船の 帆引き連れて走り行く 道の島々早過ぎて 伊平屋渡立つ波 押し添えて 残波岬もはいならで ありあり拝み御城元 弁の御嶽も打ち続き エイ 袖を連ねて諸人の迎えに出でたや 三重城 |
|
| 下り口説 | ||
| 里と思ば、のよで いやで言ふめ御宿 冬の夜のよすが 互いに語やべら |
照る太陽(テダ)や西に 布だけになても 首里みやだいりやてど ひちより行きゆる |
悪縁の結で 離ち離されめ 振り捨てて行かば 一道だいもの |
||
| 金武節(組踊「執心鐘入」) | ||||
| 去年のおれずんに 去年の若夏に 親に捨てられて 朝夕わが顔で 玉黄金一人子 あいしゆらしちおらぬ |
遊びぼれとても 友むつれとても 待ちかねて居たん 夜の暮れるぎやで 物言声すらぬ 足音もないらぬ |
|
| 子持節(組踊「女物狂」) | ||
| アマミクが始みぬ浦田原を巡ぐやい 泉口悟やい湧ぬ口悟やい 縦溝割いて開きてぃ横溝割い廻わち 畦型造て枡ぬ据してぃ 足高んうるち角高んうるち |
苦土やちぢいしてぃ甘やきぢ浮きてぃ 夏水に漬きてぃ冬水に下がるち 百とぅ十日なりばしんぬ田原に持下るち しじしじゃてぃ引分てぃ枡ぬ型に神植えてぃ 植えてぃ三日や白ふぃぢんさすい |
|
| 斎場御嶽ノロクェーナ | ||
| ヒーウスマーヤ ナマイガーヤ ムムトゥマール ティントゥマール イジャイホーヨ ナンチュホーヨ ハシラリ チュナミナリ タナミナリ ナミジュラサ |
久しぶりに 今日の吉き日 十二年ごとに 巡ってくる イザイホーよ ナンチュホーよ 洗い髪で 一重になり 二重になり 円陣の美しさよ |
|
| 久高島イザイホー「ハシララリアシビ」ティルル | ||
| 逢ぬ夜の辛さ アヌ無蔵ヨー よそに思なちやめ アヌ無蔵ヨー 恨めても ハイヤマタ 忍ぶ アヌ無蔵ヨー 恋の習ひや 恩納松下に ヤリヤリヨー 禁止の牌の立ちゆす 恋忍ぶまでの ヤリヤリヨー 禁止や無さめ スヤスヤ |
七重八重立てる ヤリヤリヨー 籬内ぬ花も 匂ひ移すまでの ヤリヤリヨー 禁止の無さめ 逢はぬ徒らに ヤリヤリヨー 戻る道すがら 恩納岳見れば ヤリヤリヨー 白雲のかかる 恋しさやつめて ヤリヤリヨー 見欲しやばかり スヤスヤ |
|
| 伊野波節 | ||
| むかしぬ あまみくが しぬくが きざしや くにたてち しまたてち みそりば しまじりん うちゃがとい たぶみつい くんがみん うちゃがとい にしぬすが ひがくいやい ひがぬすが にしくいやい ぐそだん かたれみそそち まやきぢん うちほやに むいぬかた わかさい かりぬかた わかさい |
むかしアマミクが 国を建てようとなさったら 島尻が浮き上がった 国頭も浮き上がった 西の波が 東に超えて 東の波が 西に超えて どうしようかと 神が相談なさって 森の形をお造りになり 国の形を お造りになった |
|
| 神唄 | ||
彼らは種を蒔き大地の暦を読んだ。村は大きくなり彼らを神として崇めた。彼らが死に絶えると鍾乳洞に葬り、国土と融合する岩として奉った。これが「月しろ」信仰の成り立ちだ。
池上は1970年沖縄県那覇市生まれ、後に石垣島へ。1994年早稲田大学在学中から著作が賞を受く。